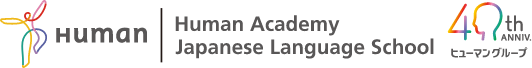Kuil ini populer sebagai tempat kekuatan, tetapi bahkan orang Jepang yang tinggal di negara tersebut secara mengejutkan tidak menyadari hubungannya dengan budaya Jepang.
Selain itu, mungkin ada orang yang mengunjungi kuil pada hari Tahun Baru atau kesempatan lain tetapi tidak mengetahui dewa apa yang disembah di sana.
Dalam artikel ini, kami ingin memperkenalkan definisi khusus tentang kuil dan berbagai dewa yang sebenarnya disembah di sana, sambil berpikir bersama Anda tentang hubungan antara budaya Jepang dan kuil.
Apa itu kuil yang memiliki hubungan erat dengan budaya Jepang?

Kuil adalah fasilitas yang memuja dewa-dewa Shinto, agama asli Jepang.
Fakta bahwa terdapat lebih dari 100.000 kuil di seluruh negeri menunjukkan betapa dekatnya orang Jepang dengan para dewa.
Struktur kuil yang khas
Kuil berfungsi sebagai tempat beribadah.
Karena alasan ini, halaman kuil biasanya memiliki gerbang torii di pintu masuk, jalan setapak menuju kuil, dan temizuya (air mancur pemurni) tempat Anda dapat menyucikan tangan. Aula utama di bagian paling belakang merupakan tempat penting tempat para dewa bersemayam, sehingga letaknya tidak terlihat.
Hubungan antara kuil dan budaya Jepang
Alasan terpenting mengapa orang Jepang pergi ke kuil adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para dewa.
Sekalipun Anda bukan penganut Shinto, banyak orang mengunjungi kuil untuk acara dan adat istiadat berikut.
- kunjungan pertama tahun ini ke kuil
- pernikahan
- Shichi-Go-San dll.
Selain menjadi tempat orang berkumpul untuk berdoa memohon keselamatan keluarga, kesehatan, dan keberhasilan ujian, kuil juga memiliki fungsi sebagai pusat kekuatan. Karena alasan ini, meskipun kuil di negara ini merupakan rumah para dewa, kuil juga berakar kuat dalam budaya Jepang sebagai tempat dukungan spiritual bagi manusia.
Berbagai dewa yang disemayamkan di kuil tersebut

Untuk memperkenalkan hubungan mendalam antara kuil dan budaya Jepang serta masyarakat Jepang, mari kita lihat karakteristik berbagai dewa yang sebenarnya diabadikan di sana.
Dewa Langit dan Bumi
Dewa-dewa langit dan bumi adalah dewa-dewa pribumi, Kunitsukami, dan Amatsukami, dewa-dewa surgawi yang tinggal di Takamagahara.
Perwakilan Kunitsukami adalah Okuninushi-no-Mikoto, dan yang paling utama dari Amatsukami adalah Amaterasu-Omikami. Selain keduanya, terdapat banyak dewa lain yang disembah di seluruh Jepang. Kuil Agung Ise, yang memuja Amaterasu-Omikami, dewa tertinggi dari delapan juta dewa, diberi nama Daijingu.
Dewa leluhur keluarga dan klan kekaisaran
Dewa-dewa seperti Amaterasu Omikami, yang diabadikan di Kuil Agung Ise, juga dianggap sebagai dewa leluhur keluarga Kekaisaran. Amanokoyane no Mikoto juga merupakan dewa leluhur klan Fujiwara yang terkenal. Kaisar-kaisar terdahulu seperti Kaisar Kanmu dan Kaisar Komei diabadikan di Kuil Heian, sebuah tempat pemujaan yang populer, dan Kaisar Ojin diabadikan di Kuil Usa di Prefektur Oita.
Semangat orang-orang hebat
Kuil ini juga mengabadikan banyak orang hebat yang aktif di zaman kuno, seperti:
- Tokugawa Ieyasu
- Sakuma Shozan
- Togo Heihachiro, dll.
Di antara orang-orang hebat, ada yang dipuja sebagai dewa dan ada yang tidak. Tidak ada aturan yang jelas atau ketentuan pasti mengenai hal ini. Umumnya dikatakan bahwa hal ini bergantung pada orang yang membangun kuil dan zamannya.
Hewan dan alam
Di kuil-kuil, gunung seperti Gunung Fuji, hutan, air terjun, dan bebatuan sering didewakan.
Misalnya, di Kuil Fushimi Inari di Prefektur Kyoto, makhluk-makhluk dengan kekuatan misterius yang disebut kenzoku dipuja sebagai utusan para dewa. Bertentangan dengan kesalahpahaman umum, mereka bukanlah rubah.
Hewan imajiner lainnya seperti naga juga dianggap sebagai simbol keberuntungan.
Dewa Asing
Kuil-kuil Jepang terkenal dengan keterbukaannya dalam menerima dewa-dewa yang datang dari luar negeri.
Misalnya, dewa-dewa India Dakini, Gozu Tenno, dan dewa-dewa azimut, yang sering disalahartikan dengan kepercayaan Inari, adalah dewa-dewa asing yang terkenal. Selain itu, fakta bahwa banyak dewa selain Shinto, seperti dewa-dewa dari Onmyodo dan Taoisme, dipuja juga menjadi salah satu alasan mengapa kuil-kuil Jepang dikunjungi oleh beragam orang, termasuk orang asing.
roh pendendam
Roh-roh pendendam, yang ditakuti banyak orang, juga disemayamkan di beberapa kuil. Inilah yang disebut kepercayaan pada roh.
Di Jepang, orang-orang menempatkan roh pendendam di kuil untuk meredakan amarah dan menangkal kutukan. Melalui kepercayaan ini, roh pendendam dianggap sebagai dewa yang membawa kedamaian bagi manusia.
Tokoh representatif dalam kepercayaan akan roh pendendam adalah Pangeran Sawara, yang meninggal dalam amarah atas kejahatan yang tidak dilakukannya, dan Sugawara no Michizane dari Dazaifu, yang meninggal sebelum waktunya. Keduanya adalah roh pendendam dan orang-orang hebat. Kuil Tenmangu, tempat Sugawara no Michizane diabadikan, adalah kuil yang dicintai oleh para siswa dan orang lain sebagai dewa pengetahuan.
ringkasan
Kuil adalah tempat di mana berbagai macam dewa disembah, termasuk tidak hanya dewa Shinto, agama asli Jepang, tetapi juga dewa leluhur para leluhur dan kaisar, serta roh pendendam.
Kuil juga berfungsi sebagai tempat orang menyampaikan rasa syukur dan permohonan kepada para dewa, sehingga banyak orang mengunjunginya sepanjang tahun untuk berbagai acara doa, kunjungan tahun baru, pernikahan, dan acara tahunan lainnya.
Kuil, yang dikelilingi alam dan pepohonan yang rimbun, juga memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan dan kekuatan. Kuil-kuil ini mudah dikunjungi siapa pun, jadi mengapa tidak memulai dengan mengunjungi kuil terdekat dan merasakan hubungan antara kuil dan budaya Jepang?
Artikel ini sebagian telah disunting ulang oleh KARUTA dari artikel aslinya yang diterbitkan di "Nihongo Biyori."
Segala bentuk reproduksi atau penggunaan konten, teks, gambar, ilustrasi, dll. dari situs web ini tanpa izin dilarang keras.