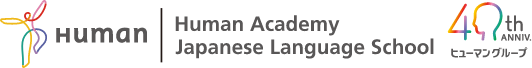「成」という漢字は「naru」「sei」と読みます。
この漢字は、何を意味するでしょうか?
【初級編】 漢字の意味を考えてみよう
この漢字は、道具を使って建物などが仕上がる様子を2つの漢字を組み合わせて表しています。
・丁…釘の形
・戊…鉞や斧
漢字の成り立ちから意味を予想できましたか?
正解は…「become」
「成」は主に「naru」と読み、例文のような場面や文章で、行為の結果や物事がまとまり、出来上がることを意味する際に使われる漢字です。
例文
「私の父が成し遂げた偉業は、後世まで語り継がれるだろう。」
(Watashi no chichi ga nashitogeta igyō wa, kōsei made kataritsugareru darou.)
My father's accomplishments will be talked about for generations to come.
【中級編】「成」の使われ方を知ろう
・成人式(seijin-shiki)
「成人(seijin)」とは、心と身体が十分に発達した人を指します。日本では、一般的に20歳以上の人を指して使われる単語です。「成人式(seijin-shiki)」は、その年に20歳を迎える人々が、公民館やホールに集まって大人になったことを感謝し、祝う行事です。毎年1月の第2月曜日は「成人の日(seijin no hi)」という祝日が定められ、この時期に全国各地で式典が行われます。
「成人式(seijin-shiki)」は、人生の中で重大な意味を持つ4大儀式「冠婚葬祭(kankonsōsai)」の中の「冠(kan)」にあたり、古くからおめでたい「晴れの日(hare no hi)」として重んじられてきました。
「成人式(seijin-shiki)」は、古来日本で行なわれてきた「元服(genpuku)」と「裳着(mogi)」という2つの儀式に由来します。この儀式は、おもに上流階級の人々の間で、通過儀礼として行なわれてきました。「元服(genpuku)」とは、12~16歳の男子が、髪を大人用の髪型に結いなおし、服装も大人のものにする儀式です。「裳着(mogi)」は、同じく12~16歳の女子が、大人が腰から下に身に着ける衣服「裳(mo)」を身に着ける儀式です。
古来の儀式が現代の「成人式(seijin-shiki)」のように、多くの人々が関わる式典になったきっかけは、1946年に埼玉県で開催された「青年祭(seinen-sai)」という行事と言われています。「青年祭(seinen-sai)」は、戦後の暗い気分を払拭して、これからの世代を担う若者たちを盛り上げていくために行われました。この行事が徐々に全国へ広まり、「成人式(seijin-shiki)」は一般的なものになりました。今も昔も、大人になる節目を重んじる文化は変わりません。
例文
「成人式で久々に会った友人たちは、人生を楽しんでいるようで安心した。」
(Seijin-shiki de hisabisa ni atta yūjin-tachi wa, jinsei wo tanoshinde iru yō de anshin shita.)
I was relieved that the friends I met for the first time in a long time at the coming-of-age ceremony seemed to enjoy life.
「成」と似ている漢字
日本には、「成」という漢字に似たつくりの漢字が多くあります。たとえば、次のような漢字があります。
・戈(hoko)
両刃の剣に、長い柄が付いた武器を意味する漢字です。「銅戈(dōka)」と呼ばれる、今から約1,700~2,300年前の弥生時代につくられた青銅の戈は、広島県の文化財として保存されています。
・戉(masakari)
斧の形をした大型の武器を意味する漢字です。大きな木を伐採するときにも使われます。日本の代表的な童話のひとつ「金太郎(kintarō)」では、主人公「金太郎(kintarō)」が大きな戉を担いでいます。
・戍(jyu/mamoru)
武器等を持って攻撃から守ることを意味する漢字です。現代では、あまり使われる機会は少ない漢字ですが、「成」や「戉」などと間違われやすい漢字として位置付けられています。
これらの漢字は、すべて「ほこがまえ」とよばれる、武器の意味を含んだ部首を使っています。「成」という漢字も、武器などを使って建物を仕上げる様子から成立したように、漢字の部首を見ることで、本来の意味を理解することができます。
例文
「博物館には、古代から使用されていたとされる戈と戉が、展示されている。」
(Hakubutsukan ni wa, kodai kara shiyō sa rete ita to sa reru hoko to masakari ga, tenji sa rete iru.)
The museum exhibits the dagger-axe and the broad-axe, which are said to have been used since ancient times.
【上級編】「成」を使った諺や慣用句を使ってみよう!
「成」は、前向きな文脈や、仕上げる過程や仕上がった様子を伝える文脈で使われることが多い漢字です。日本人がよく使う「成」を使った表現をご紹介します。
・為せば成る(nase ba naru)
たとえできそうもないことであっても、強い意志を持ってやり通せば、必ず実現できるという意味です。江戸時代後期に、「上杉鷹山(Uesugi Harunori)」という人物が「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり(Nase ba naru, nasane ba naranu nanigoto mo, naranu wa hito no nasanu nari keri)」と家臣に伝えた言葉に由来しています。何事も挑戦しなければ、得られるものも得られないということが分かる言葉です。「為せば成る(nase ba naru)」は、座右の銘として自己紹介に使われたり、挑戦することを恐れている人を激励したりする際によく使われます。
例文
「為せば成るという言葉を思い出して。もう少し頑張れば、きっと志望校に合格できるよ。」
(Nase ba naru to iu kotoba wo omoidashite. Mōsukoshi ganbare ba, kitto shibōkō ni gōkaku dekiru yo.)
Remember the saying that if you do it, it will definitely come true. If you work a little harder, you will surely be able to pass the school of your choice.
・失敗は成功のもと(shippai wa seikō no moto)
失敗しても、その原因を追究し改善していくことで、成功に近づくことができるという意味です。失敗したことをそのままにして、やり方や考え方を改善しようとする姿勢がなければ何度も同じような失敗を繰り返してしまうという戒めの意味も込められています。
例文
「あのとき、先生が失敗は成功のもとと言ってくれたから、この絵が描けました。」
(Ano toki, sensei ga shippai wa seikō no moto to itte kureta kara, kono e ga egakemashita.)
At that time, my teacher said that failure was the source of success, so I was able to draw this picture.
・育成(ikusei)
教育や訓練を施し、育てることを意味します。多くの企業では、自社で活躍し、社会に貢献できる人物を育てるために人材の育成が行われています。
例文
「私の会社では、若手社員の育成に力を入れています。」
(Watashi no kaisha de wa, wakate shain no ikusei ni chikara wo irete imasu.)
At my company, we are focusing on training young employees.
・合成(gousei)
2つ以上のものを合わせて1つの状態にすることを意味します。
例文
「この街の風景は、どう見ても合成写真だよ。」
(Kono machi no fūkei wa, dō mite mo gōsei shashin da yo.)
The scenery of this city is a composite photograph no matter how you look at it.
・完成(kansei)
物事が完全にでき上がることや仕上げることを意味します。
例文
「家族みんなで住める大きな家が、ついに完成した。」
(Kazoku min'na de sumeru ōkina ie ga, tsuini kansei shita.)
A big house where the whole family can live has finally been completed.
「成」の漢字の意味と使い方をご紹介しました。日本の漢字の独特な表現や使い方に興味を持った方は、Let’s Play KARUTAでさまざまな漢字の意味や成り立ちを見てみてはいかがでしょうか?