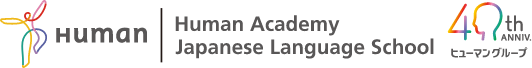「寒」という漢字は「kan」「samu」と読みます。
この漢字は、何を意味するでしょうか?
【初級編】 漢字の意味を考えてみよう
この漢字は、人が屋内で寒さをしのごうとする様子を4つの記号を組み合わせて表しています。
・ウ…家屋、屋根
・#…枯草
・人…人の象徴
・冫…氷、冷気
漢字の成り立ちから意味を予想できましたか?
正解は…「cold」
「寒」は主に「samu」と読み、例文のような場面や文章で、気温が低下していることを身体で感じるときに使われる漢字です。
例文
「昼間は暖かかったのに、夕方になって急に寒くなってきた。」
(Hiruma wa atatakakatta no ni, yūgata ni natte kyū ni samuku natte kita.)
It was warm in the daytime, but suddenly became cold in the evening.
【中級編】 日本が寒くなる時期と寒さで有名な場所を知ろう!
・小寒(shōkan)と大寒(daikan)
日本には、1年を24分割し、それぞれに季節を表す言葉をつけた「二十四節季(nijyūshi-sekki)」と呼ばれる暦の指標があります。「二十四節季(nijyūshi-sekki)」の中には、「小寒(shōkan)」と「大寒(daikan)」と呼ばれる季節があります。
「小寒(shōkan)」は、冬の寒さが厳しくなり始める1月5日頃~1月19日までの期間を指します。「小寒(shōkan)」の時期は、1年の始まりの時期でもあるので、今年1年の健康や豊作を祈って「七草粥(nanakusagayu)」を食べます。「七草粥(nanakusagayu)」は、7種類の若菜が入ったお粥です。「七草粥(nanakusagayu)」に使われる7種類の若菜は、「セリ(seri)」「ナズナ(nazuna)」「ゴギョウ(gogyō)」などがあり、ビタミンが豊富に含まれていて、消化を助けるはたらきもあるので、お正月で疲れた胃をいたわる効果があります。
「小寒(shōkan)」が過ぎると、「大寒(daikan)」と呼ばれる季節が訪れます。「大寒(daikan)」は、冬の寒さが最も厳しくなる1月20日頃から2月3日までの期間を指します。「大寒(daikan)」の時期には、「大寒たまご(daikan-tamago)」と呼ばれる、「大寒(daikan)」に産まれた卵を食べることがあります。「大寒たまご(daikan-tamago)」は、冬の厳しい寒さの中、たくさんの餌を食べた鶏から産まれる卵です。そのため、「大寒たまご(daikan-tamago)」は栄養豊富です。「大寒たまご(daikan-tamago)」を食べると、寒い時期でも健康に過ごすことができると言われています。
・寒中見舞い(kanchū-mimai)
「小寒(shōkan)」から「大寒(daikan)」までの期間は「寒中(kanchū)」と呼ばれます。この時期は、寒さで体調を崩しやすい時期なので、親戚や知人などの健康を気遣って「寒中見舞い(kanchū-mimai)」と呼ばれる挨拶状を送る習慣があります。近年は、喪中のため、正月に送る習慣のある年賀状を送れなかった場合や、年賀状の返事として送られることも多いです。
例文
「今日の午後、父は寒中見舞いをポストに投函しに行く予定だ。」
(Kyō no gogo, chichi wa kanchū mimai wo posuto ni tōkan shi ni iku yoteida.)
This afternoon, my dad will go to mail a winter greeting card.
・日本一寒い町「北海道陸別町」
日本の北側、北海道の東に位置する「陸別町」は、人口約2,500人と小さな町ながら、日本で最も寒い地域として知られています。「陸別町」は、周囲が山に囲まれた盆地なので、冷気がたまりやすい地形をしています。冬の平均最低気温は、約マイナス20度にもなります。マイナス20度の気温は、髪の毛、まつげなども凍ってしまうほどの寒さです。
ちなみに、日本の南側に位置する沖縄県の冬の平均最低気温は約15度なので、同じ国の中でも北側の北海道と南側の沖縄県では、かなり気温差があります。
「陸別町」では、日本一寒いことを全国にアピールするために、「しばれフェスティバル(shibare-fesutibaru)」と呼ばれるイベントを催しています。「しばれる(shibareru)」とは、北海道の方言で、寒いことや冷えこんでいることを意味する単語です。北海道では、氷点下の気温のときに、「しばれる(shibareru)」という言葉を使うことが多いようです。
例文
「こんなにしばれる日なのに、うっかりマフラーを忘れてきてしまったよ。」
(Kon'nani shibareru hi na no ni, ukkari mafurā wo wasurete kite shimatta yo.)
I inadvertently forgot my scarf even though it was such a chilly day.
【上級編】「寒」を使った諺や慣用句を使ってみよう!
「寒」は主に、冬の時期に使われることの多い漢字です。日本人がよく使う「寒」を使った表現をご紹介します
・寒空(samuzora)
冬の澄み切った真っ青な空や、いまにも凍りそうな空の様子を表すときに使います。「寒空(samuzora)」は、十七音で表現する俳句の中でも、季節を表す言葉、「季語(kigo)」として使われます。
例文
「寒空の下、子供たちは元気にサッカーをしている。」
(Samuzora no shita, kodomo-tachi wa genki ni sakkā wo shite iru.)
Under the cold weather, the children are playing soccer energetically.
俳人 小林一茶の俳句
「寒空のどこでとしよる旅乞食」
(Samuzora no doko de toshiyoru tabikojiki.)
Where will the beggars grow old in the cold weather?
・寒波(kanpa)
冬の時期に、極や高緯度付近で冷却された空気が、中緯度や低緯度地方の広い範囲に流れ出す気象を意味します。日本付近の寒波は、日本海側では大雪を、太平洋側では冷たい風をもたらします。寒波が日本に到来する時期は、農業や交通など、社会活動に影響を及ぼすこともあります。
例文
「せっかくドライブに行こうとしたのに、寒波の影響で路面は凍結してしまっている。」
(Sekkaku doraibu ni ikou to shita no ni, kanpa no eikyō de romen wa tōketsu shite shimatte iru.)
I tried to go for a drive, but the road surface was frozen due to the cold wave.
・寒気(kanki/samuke)
「寒気」には2つの読み方があります。「寒気(samuke)」と読むときは、人が寒さを感じるときや、人が感じる寒さの程度を意味します。「寒気(kanki)」と読むときは、寒く感じられる気象を意味します。同じ漢字をつかっていても、読み方によって意味が異なるので注意が必要です。
例文
「朝から晩まで寒気にさらされていたからだろうか、今日は寒気が止まらない。」
(Asa kara ban made kanki ni sarasarete ita kara darou ka, kyō wa samuke ga tomaranai.)
Perhaps because I was exposed to the cold air from morning till night, I can't stop feeling cold today.
・暑さ寒さも彼岸まで(atsusa samosa mo higan made)
日本には、「春彼岸(haru-higan)」と「秋彼岸(aki-higan)」呼ばれる日があり、どちらも昼夜の長さがほとんど同じになります。「春彼岸(haru-higan)」を過ぎれば、日照時間は長く、寒さも和らいでいきます。反対に、「秋彼岸(aki-higan)」を過ぎれば、日照時間は短く、暑さも和らいでいきます。「暑さ寒さも彼岸まで(atsusa samosa mo higan made)」は、おもに、暑さや寒さが収束してもよい頃なのに、まだまだ変わる気配がないと感じるようなとき、「もう少しで過ごしやすくなるだろう」と伝えるときに使います。
例文
「暑さ寒さも彼岸までと言うけれど、一向に春の訪れを感じられない。」
(Atsusa samusa mo higan made to iu keredo, ikkōni haru no otozure wo kanji rare nai.)
It's said that no heat or cold lasts over the equinox, but I can't feel the coming of spring at all.
「寒」の漢字の意味と使い方をご紹介しました。日本の漢字の独特な表現や使い方に興味を持った方は、Let’s Play KARUTAでさまざまな漢字の意味や成り立ちを見てみてはいかがでしょうか?